こんにちは、福井県で農業を学んでいる大学生の草男です。僕たちの農業サークルでは、現在20aほどの畑で実際に野菜を育てていて、収穫物の販売まで行うほど本格的な活動をしています。今回は、そんなサークル活動の中で取り入れた「作業工程管理」についてお話ししたいと思います。
作業工程管理ってそもそも何?
「作業工程管理」とは、ざっくり言えば**「いつ・誰が・どこで・何をしたか」をしっかり記録して、作業のムダやミスを減らす管理方法**のこと。もともとは製造業などでよく使われている言葉ですが、農業でも同じように、「誰が何をしたのか」「その作業にどれくらい時間がかかったのか」を可視化することで、次の作業の計画を立てやすくなったり、作業の効率を上げたりできます。
なぜLINEで共有?その背景
僕たちのサークルは、メンバーの出入りが多く、同じ日に来られる人数がバラバラなんです。さらに、作業内容も日によって「草取り」「播種」「収穫」「販売用の袋詰め」など多岐にわたります。
それまでは作業の報告を口頭で伝えたり、メモに書いていたんですが、それでは**「何をやったのか誰も分からない」「次に何をすべきか見えにくい」**という問題が出てきました。
そこで導入したのが、LINE Bot+スプレッドシートによる作業日誌の共有です。
実際にどうしてるの?
仕組みはシンプルです。
各メンバーが「出勤」「退勤」「作業内容」をLINEに送ると、自動でGoogleスプレッドシートに記録されるようになっています。
たとえば、こんな感じで投稿します。
出勤
作業:畝づくり・播種
退勤すると、スプレッドシートには日付・名前・作業内容・時間が自動で記録されていきます。
これによって、誰が何時間働いたか、どの作業にどれだけ時間がかかったか、次に何をすべきかがすぐ分かるようになりました。
実は、最初は大変やったんです…
正直、最初はLINEやグループに写真や報告を流しているだけで、「全体として何月何日に何をやったか」がまったく整理されていませんでした。
過去の作業を確認しようとすると、LINEを何ヶ月も遡ったり、メンバーのスマホの写真を探したり…。それでも出てこないこともあって、来年以降の記録としては使い物にならないと感じていました。
それに、今後もし補助金の申請や外部への報告が必要になったとき、**「いつ・誰が・どれくらい作業していたか」**という情報は必須になります。時間の短縮効果や作業量の証明にもなりますし、ちゃんとデータとして残しておく価値は大きいと考えました。
だから、LINE公式アカウントを導入した
そこで思いついたのが、ChatGPTを活用しながらLINE公式アカウントを使ったシステム構築でした。
なぜLINEかというと、Googleフォームのように毎回リンクに飛んだりQRコードを読み込んだりするのって、地味に面倒なんですよね。
でもLINEであれば、ふだんから使っているツールなので、「出勤」「作業」「退勤」と打つだけでOK。しかも送信時刻・日付は自動で記録されるので、メンバーにとってもストレスがないんです。
システムの仕組みは?
ざっくり流れをまとめるとこんな感じです。
- LINE公式アカウントを開設
- **Google Apps Script(GAS)**を使ってLINE Botを作成
- LINEで送られたメッセージをGoogleスプレッドシートに自動記録
- スプレッドシート側で、名前・IDを紐づけて集計表を自動作成
これによって、作業者ごとの記録、全体作業時間、作業内容の一覧などが自動で可視化されます。
もちろん無料で始められる範囲で構築できるので、学生サークルにもピッタリです。
継続性・拡張性もバッチリ
この方法のいいところは、継続しやすいことと、将来的に拡張もできること。
LINEのアカウントにログインすればすぐ記録できるし、名前の自動変換も可能なので、記録ミスも防げます。
今後は、月ごとのグラフや、年間の作業報告書などにも活用していきたいと考えています。
まとめ
農業をチームでやる上で、作業工程の記録は「面倒だけど超重要」な作業です。
でも、LINEとスプレッドシートをうまく組み合わせれば、誰でも簡単に・無料で・続けやすく工程管理を始められます。
僕たちもこの仕組みを2時間ほどで形にできたので、気になった方はぜひチャレンジしてみてください。
今後、このシステムの作り方も詳しく記事化して紹介していく予定です!

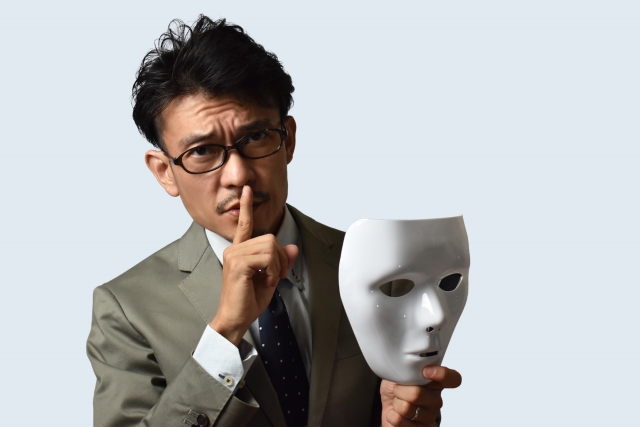


コメント