一見、ツヤのある緑の葉が美しく、近くで見ると小さな白い花まで咲く、観賞価値すら感じられる草――
でもその正体は、在来植物を圧倒的な勢いで駆逐し侵略的外来植物と恐れられる。
その名はミドリハカタカラクサ(Tradescantia fluminensis ‘Viridis’)。
人の目には美しく映っても、自然界では深刻な問題を引き起こす、静かで強烈な侵略者です。
① ミドリハカタカラサのプロフィール
- 学名:Tradescantia fluminensis ‘Viridis’
- 分類:ツユクサ科ムラサキツユクサ属
- 原産地:南アメリカ(アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ)
- 花期:夏〜秋(小さな白い三弁花を咲かせる)
- 草丈:10〜30cmほど(地を這うように広がる)
- 生育環境:湿り気のある林縁、小川沿い、沢沿いなど、自然度の高い場所を好む
もともとは観賞用に導入された植物ですが、今では世界各地で生態系を脅かす外来種として扱われています。

② 美しさの裏にひそむ“緑の侵略者”
つやつやした緑の葉と可愛らしい白い花。その美しさに、園芸用として植えられることもあります。
しかし、いったん自然の中に入り込むとその様相は一変。在来植物の上に覆いかぶさるように広がり、光を奪い、水を奪い、土壌までも独占。
まさに“緑のじゅうたん”のように、地面をびっしりと覆い尽くしてしまいます。
特に湿った環境では勢いが止まらず、他の植物の芽生えや成長すら阻害してしまうほど。
そのため、ニュージーランドやオーストラリアなどでは「要注意外来生物(Unwanted Organism)」に指定され、野外への放出が法律で禁止されているほどです。
③ 種がなくても…1cmで復活する恐怖の再生力
ミドリハタカラクサは、種子をほとんど作りません。ではなぜこれほど増えるのか――
それは、「栄養繁殖」と呼ばれる再生能力があるからです。
たった1cmほどの茎や根の断片があれば、そこから新しい株が復活。
つまり、ちょっとでもちぎれて残っていれば、それがどんどん増えて広がっていくのです。
草刈りや除去をしても、その作業中に断片が落ちたり、水に流されたりするだけで別の場所で再発。
まさに“しぶとさの権化”とも言える恐るべき繁殖力です。
④ 生息場所は“自然が豊かなところ”ほど危険(体験談)
ミドリハカタカラクサが特に好むのは、「人の手が入りにくい自然地」。
湿り気のある林内や小川沿い、渓流沿いなど、生態系が豊かな場所ほど侵入された際の影響が深刻になります。
実は、筆者自身も高校時代に体験があります。
自然観察の一環で訪れた、自然豊かな里山の川辺――そこは透き通った水が流れる美しい場所でした。
その川のすぐそばに、ツヤのある緑の葉が一面に広がっていて、「ツユクサかな?」と思って近づいてみたんです。
でも、よくよく調べてみると、それがミドリハカタカラクサだということが判明。
そのときの驚きと、「こんなに自然が豊かな場所にも外来種が入ってくるのか…」というショックはいまでも覚えています。
もし、山歩きや川沿いの散策で「やけに一面が緑でツヤツヤしてるな…」と思ったら、それがミドリハタカラクサの可能性も。
拡大初期の発見が、被害の拡大を防ぐ重要なカギです。

⑤ ミニコラム|乾燥は唯一の弱点
あまりに強いこの植物にも、実は唯一の弱点があります。それが乾燥。
日差しが強く、風通しの良い乾燥地では定着が難しく、葉が枯れてしまうことも。
ただし、これはあくまで“乾燥した場所では”という話。
ジメジメとした林内や水辺では、勢いが止まりません。むしろ繁殖のスピードが増します。
つまり、場所を選ばずに放任してしまうと危険なのです。
⑥ 利用法はある?
園芸植物として流通していた過去があるため、現在も一部の園芸店で取り扱われていることがあります。
ただし、自然に近い場所での使用は絶対NG。
見た目が似ている園芸品種との区別が難しいこともあり、「知らずに自然に植えていた…」というケースもあるため注意が必要です。
⑦「ミドリハカタカラクサ」を調べるのにおすすめの本
『帰化&外来植物 見分け方マニュアル 950種』森昭彦(秀和システム)
ムラサキツユクサやその他の類似植物との違いが図解つきでとてもわかりやすく解説されており、細かい特徴をしっかり比較しながら見分けることができます。
とくにミドリハタカラクサのように見た目が美しい植物でも、外来種かどうか見極めたいときに非常に役立ちます。
また、各ページにはコラムや補足情報も豊富で、読み物としても楽しめる内容。外来植物や帰化植物をしっかり学びたい方には、間違いなくおすすめできる一冊です。
植物観察が趣味の方や、自然保全・環境問題に関心のある方にもぴったりの内容となっています。
⑧ 駆除・対策について
駆除の基本は根ごと抜いて焼却処分。
とにかくちぎれた断片からでも再生するため、「刈るだけ」「抜いて放置」は逆効果。
ゴミ袋で処分したとしても、処理場で再発するリスクもあります。
湿った環境で定着する前に、“早期発見・早期除去”が何よりも重要。
川辺や山間部などで見つけた場合は、地元の行政や保全団体と連携するのも効果的です。
【2025年最新】除草剤おすすめ10選|効果が高くて安全!使い方・選び方・雑草ごとの対策も解説
>駆除方法の詳しい情報は、[こちらのミドリハカタカラクサ対策ガイド(仮リンク)]をご覧ください。
⑨ まとめ
ミドリハカタカラクサは、見た目の美しさに反して非常に強い繁殖力と再生力を持つ外来植物です。
湿った自然環境では特に勢いを増し、在来の植生を根こそぎ奪ってしまう力を持っています。
一度定着すれば、駆除には大きな労力と時間が必要。
だからこそ、「美しいけどちょっと気をつけたほうがいい植物」として認識することが、自然を守る第一歩になります。
おすすめ記事
雑草ドットコムが目指す場所|図鑑じゃ終わらない、“草の魂”を届けるメディアへ
【雑草解説】ハルジオンとは?特徴・見分け方・ヒメジョオンとの違いを徹底解説!


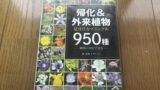


コメント